就労継続支援B型事業所とは?特徴やA型との違い
就労継続支援B型事業所とは、精神障害や身体障害、知的障害、難病などを理由に一般企業などで働けない方々に向け、福祉サービスの一貫として設けられている就労の場を言います。
事業所との雇用契約を結ぶことはなく、自分で働いた分に応じて工賃を支給される点が特徴。工賃をもらうだけではなく、今後も働いていくための訓練を行ったり、仕事を通じてスキルを磨いたりすることも、就労継続支援B型事業所の目的となります。
ここでは、就労継続支援B型事業所の特徴やA型事業所との違い、事業所の利用方法などについて詳しくご紹介しています。
就労継続支援B型事業所を利用できるのはこんな人
就労継続支援B型事業所の利用対象者は、精神障害(発達障害を含む)や身体障害、知的障害、難病などをお持ちの方となります。また、それらの障害をお持ちであることに加え、主治医から事業所の利用を認められた方のうち、以下のどれかに該当する方が、就労継続支援B型事業所を利用できるとされています。
- 就労経験があり、年齢・体力的な面で一般企業で働くことが困難になった方
- 50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受給している方
- 上の2つに該当しない方のうち、就労移行支援事業者等のアセスメントにより、就労面の課題が把握されている方
就労継続支援B型事業所は、特別支援学校の卒業直後から利用することはできません。就労経験がある方、または就労移行支援事業所を利用した方のみが利用できるのが原則です。
ただし制度の運用については自治体で異なる場合があるため、実際に就労継続支援B型事業所の利用を検討する際には、お住まいの自治体の窓口までお問い合わせください。
就労継続支援B型事業所とA型事業所の違い
就労継続支援A型事業所もB型事業所と同じで、何らかの障害等をお持ちの方に向けた就労の場です。
ただしB型事業所では事業所と就労者の間に雇用契約が結ばれない一方、B型事業所では両者の間に雇用契約が結ばれる点が大きな違い。雇用契約が結ばれる以上、A型事業所で働く方には社会保障も約束されます。
また、B型事業所で働く方には年齢制限がありませんが、A型事業所で働く方には原則として18~65歳と年齢制限がある点も両者の大きな違いとなります。
なお就労者に支払われる給料を比較した場合、B型よりもA型のほうが高くなることが一般的です。ただし、原則としてA型事業所では決まったスケジュールで仕事をしなければならないことに対し、B型事業所では自分のペースで無理なく仕事をすることができます。体調に不安のかる方にとっては、B型事業所のほうが適しているとも言えるでしょう。
就労移行支援事業との違い
B型事業所やA事業所では、その事業所で働くこと自体を目的としていますが、就労移行支援事業では、事業所での就労訓練を通じて一般企業への就職を目指すことを目的としています。
就労訓練の場であることから、原則として給料が支払われることはありません(事業所によっては工賃が支払われることもある)。利用対象年齢は原則65歳未満で、利用期間は原則2年となります(延長できる場合もある)。
就労継続支援B型事業所の作業内容と勤務時間
就労継続支援B型事業所の作業内容は、主に次のようなものです。
- パンなどの製造
- クリーニング
- 梱包・発送作業
- 手工芸品の製作
- ミシンを使った作業
- 部品加工
- パソコンでの簡単な入力作業、など
就労継続支援B型事業所の勤務時間には基本的に決まりがなく、利用者の自由に設定できます。「週1日×1日1時間」でも構いません。ただし事業所によっては、勤務時間に関する一定の条件がある場合もあるため、利用する際には事前によく確認しましょう。
参考までに、A型事業所の主な作業内容は次のようなものです。
- パソコンでの入力作業
- カフェやレストランでの接客・調理
- ホテルの清掃
- Webデザイン、など
A型事業所での作業内容は、一般企業での仕事内容と大きく違いません。
就労継続支援B型事業所の工賃
厚生労働省が公表している資料(※)によると、令和3年度における就労継続支援B型事業所の平均工賃は次のとおりです。
- 月額:16,507円
- 時間額:233円
令和2年度に比べ月額で104.6%、時間額で10.5.0%と上昇しています。
参考までに、同じ資料に掲載されている就労継続支援A型事業所の平均賃金は次のとおりです。
- 月額:81,645円
- 時間額:926円
令和2年度に比べ月額で102.5%、時間額で103.0%と上昇しています。
※参照:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html)
就労継続支援B型事業所の利用料金
就労継続支援B型事業所は働いて給料をもらう場である一方、福祉サービス提供の場という側面も持つことから、利用する際には料金がかかります。原則として利用料金の9割が国・自治体の負担となり、1割が自己負担となる形です。
福祉サービスである以上、利用する日数が多くなればなるほど利用料金も上がりますが、世帯の収入に応じて自己負担の上限額が設定されているため、たくさん働いたとしてもさほど不安に思う必要はありません。利用料金の上限額は次のとおりです。
- 生活保護受給世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満/※):9,300円
- 上記以外:37,200円
※入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者を除く
就労継続支援B型事業所の利用方法
事業所に問い合わせる
まずは、気になる事業所に問い合わせます。事業所はハローワークや自治体の障害福祉課窓口で公開されているので、ご自身で確認してみましょう。
問い合わせ方法は、自分で電話等で問い合わせるか、またはハローワーク等の窓口担当者から問い合わせる形となります。
事業所へ見学に行く
問い合わせた事業所へ見学に行ってみましょう。
見学は必須ではありませんが、実際に長く働くかもしれない事業所である以上、心地よく働いていけるかどうかを確認するため、見学しておくことをおすすめします。
事業所の仕事内容や雰囲気、職員や利用者の様子などのほかにも、休憩スペースやトイレなどの設備面も確認しておくようにしましょう。
気になる事業所が複数あれば、それぞれの事業所を見学して比較してみるようおすすめします。
面接
働きたい事業所を1つに絞り込んだら、改めて事業所に問い合わせて面接を受けます。一般企業の就職面接とは異なり、履歴書を持参する必要はありません。
面接では、日常生活で困っていることや現在の生活状況などが聞かれます。一般企業の就職面接のような張り詰めた雰囲気ではないので、普段通りにリラックスして面接を受けましょう。
受給者証の申請
面接に合格したら、自治体に赴いて障害福祉サービスの受給者証の発行申請を行います。自治体から支援給付金を受給するための大事な証明書です。
受給者証の申請とあわせて、本人への聞き取り調査に基づいてサービス等利用計画書の作成が行われますが、基本的には担当者の指示通りに動いていれば滞りなくすべての手続きが完了するので、安心しましょう。
受給者証は、申請から2週間~1か月ほどで手元に届きます。
利用開始
事業所と相談し利用開始日を決めた上で、事業所の利用がスタートします。利用する初日は印鑑等が必要になることもあるため、必要なものを忘れないよう持参しましょう。
まとめ
就労継続支援B型事業所の特徴について、A型事業所との比較も交えながらご紹介しました。
B型事業所は、A型事業所に比べると給料が低めになることが一般的です。ただし、事業所へ通う目的は給料をもらうことのほかにも、就労訓練ができるなどの福祉サービスの享受にもあります。条件を満たしているという理由で、単純に給料の高いA型事業所を選ぶことは早計です。
B型とA型のどちらが向いているかを考える1つの基準は、利用者の体調でしょう。A型事業所の中にはフルタイムで週5日働くところもありますが、そのようなペースで働いていける自信がなければ、B型事業所を検討するようおすすめします。
ご自身の体調について主治医やご家族とも相談のうえ、B型とA型の適したほうを選ぶようにしましょう。
札幌の就労継続支援B型事業所3選
おしゃれな空間でお仕事できる
(ハナリノ)

| PC業務 |
| 小物制作 |
| ネイルチップ制作 |
| イラスト作成(ペンタブ) |
- 美容系のおしゃれな仕事に挑戦したい方におすすめ
| 地下鉄「北18条駅」 |
| 徒歩1分 |
地域に貢献するお仕事ができる
SAPPORO
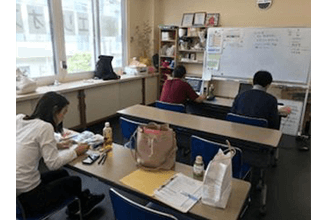
| PC業務 | 販売業務 |
| 小物制作 | - |
| 軽作業 | - |
| 委託業務 | - |
- ボランティア活動に興味がある方におすすめ
| 市電「西線6条」電停 |
| 徒歩3分 |
専門スタッフの指導が受けられる
マネジメント

| PC作業 |
| 小物制作 |
| 軽作業 |
| 委託業務 |
- PCスキルの習得を目指したい方におすすめ
| 東西線「南郷7丁目駅」3 |
| 徒歩1分(WORK LIFE店) |
※このサイトで紹介している就労継続支援B型事業所15社[※1]の中から、4つ以上の作業ジャンルを実施している3社を厳選しました。
[※1]このサイトではGoogleで「就労継続支援B型 札幌」を検索した上位15社(2021年4月22日時点)を掲載しています。